生産者と消費者の提携
「提携」の方法の指針 「提携10か条」について
日本有機農業研究会は、生産者と消費者が協力して有機農業を進める活動の方法について、1978年11月、第4回大会で「生産者と消費者の提携の方法」を発表しました。これは、有機農業による生産物を農家から消費者へ渡し・受け取る方法は、「過去にも現在にも、国内にも国外にも、われわれが手本とすべき事例は見当たらない」ことから、各地で有機農業の先駆者たちが自ら独創的に工夫をして行っていた実践の経験を集め、実践者が集まり、話し合ったものを基に、創設者一楽照雄が今後のあり方として取りまとめた実践に裏づけられた指針です。これは、翌79年2月、『土と健康』に、一楽さんのコメント付きで掲載されました(2007年4・5月合併号に復刻版掲載)。それ以降、「提携10原則」「提携10か条」と呼ばれ、会の基本的な活動の指針となっています。
「提携」(産消提携、生消提携とも呼ばれる)は、単なる「商品」の産地直送や売り買いではなく、人と人との友好的つながり(有機的な人間関係)を築くなかで進めます。生産者も消費者も、農法を変革するだけでなく、「農産物の選別・包装を簡略化する」、「自主配送を原則にする」、「自給する農家の食卓の延長線上に、都市生活者の食卓をおく」、「間引き菜から董(とう)が立つまで食べる」「一物全体食」などに努めます。消費者も農作業の手伝いなどを通して農業に触れ、農業を理解すること、互恵精神に基づき、話し合って価格 を決めること、学習活動を重視するなど、理想に向かって共に有機農業を実践、自然を大切にした有機農業的な生活をしていくことを説いています。
生産者と消費者の提携の方法(提携の10カ条)
■相互扶助の精神
1.生産者と消費者の提携の本質は、物の売り買い関係ではなく、人と人との友好的付き合い関係である。すなわち両者は対等の立場で、互いに相手を理解し、相扶け合う関係である。それは生産者、消費者としての生活の見直しに基づかねばならない。
■計画的な生産
2.生産者は消費者と相談し、その土地で可能な限りは消費者の希望する物を、希望するだけ生産する計画を立てる。
■全量引き取り
3.消費者はその希望に基づいて生産された物は、その全量を引き取り、食生活をできるだけ全面的にこれに依存させる。
■互恵に基づく価格の取決め
4.価格の取決めについては、生産者は生産物の全量が引き取られること、選別や荷造り、包装の労力と経費が節約される等のことを、消費者は新鮮にして安全であり美味な物が得られる等のことを十分に考慮しなければならない。
■相互理解の努力
5.生産者と消費者とが提携を持続発展させるには相互の理解を深め、友情を厚くすることが肝要であり、そのためには双方のメンバーの各自が相接触する機会を多くしなければならない。
■自主的な配送
6.運搬については原則として第三者に依頼することなく、生産者グループまたは消費者グループの手によって消費者グループの拠点まで運ぶことが望ましい。
■会の民主的な運営
7.生産者、消費者ともそのグループ内においては、多数の者が少数のリーダーに依存しすぎることを戒め、できるだけ全員が責任を分担して民主的に運営するように努めなければならない。ただしメンバー個々の家庭事情をよく汲み取り、相互扶助的な配慮をすることが肝要である。
■学習活動の重視
8.生産者および消費者の各グループは、グループ内の学習活動を重視し、単に安全食糧を提供、獲得するためだけのものに終わらしめないことが肝要である。
■適正規模の保持
9.グループの人数が多かったり、地域が広くては以上の各項の実行が困難なので、グループ作りには、地域の広さとメンバー数を適正にとどめて、グループ数を増やし互いに連携するのが、望ましい。
■理想に向かって漸進
10.生産者および消費者ともに、多くの場合、以上のような理想的な条件で発足することは困難であるので、現状は不十分な状態であっても、見込みある相手を選び発足後逐次相ともに前進向上するよう努力し続けることが肝要である。
(1978年11月25日、第4回全国有機農業大会で発表。ただし項見出しは後日追加)
日本有機農業研究会の「提携」を軸にした有機農業運動
IFOAMアジア地域会議(1993年8月19-22日、埼玉県飯能市)
◇CONTENTS
1. 日本有機農業研究会の概要
2. 背景・・工業化と農業近代化の進展
3. 有機農産物流通の現状
(1) 最初は「提携」から
(2) 増える市場流通
(3) 表示規制の現状と問題点
4. 市場流通指向型の生産の問題点
5. 「提携」を軸にした有機農業運動
(1) 「提携」の基本理念
(2) 「提携」の方法
6. 地域自給と自立のための有機農業運
7. 今後の方向
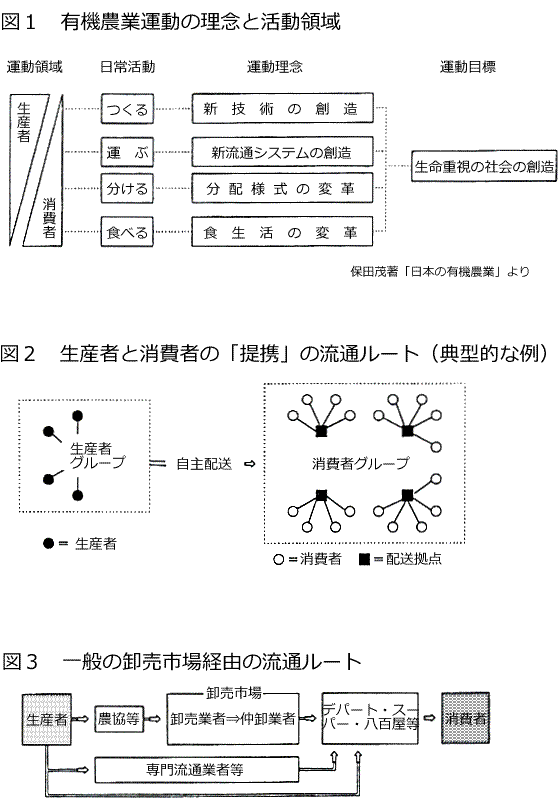
1. 日本有機農業研究会の概要
日本有機農業研究会(以下、有機農研と略す)は、有機農業を進め、広げるための生産者と消費者を中心とした会で、1971年10月に結成された非営利の自主的な組織である。財源はすべて会員からの会費で賄われており、政府・企業などからの援助は受けず、機関誌には広告を一切掲載しないで独立性を保持している。
有機農研が結成された1970年前後は、国民総生産(GNP)の実質成長率・年平均10%以上という世界に類を見ない「高度経済成長期」のただ中であり、工業化が急速に進められるなかで、水・大気・土壌の汚染などの公害や環境破壊がひき起こされ、悲惨な水俣病などの公害病、有害化学物質の混入による食品公害事件が相次いで起きた。生産第一の効率が追求されるなかで、食品添加物が多用された粗悪な食品があふれ、農薬・化学肥料を多投する近代化農業が推進され、生命・暮らし、環境をむしばみ始めた時代であった。
食べ物の安全性に強い不安を抱いた消費者たちは、大都市を中心に無添加食品や安全な卵・牛乳などの「安全な食べ物を手に入れる運動」を起こした。一方、農薬による直接的な人体被害や、農薬・化学肥料による家畜の異変や土の疲弊を感じとった生産者は、各地で有機農業を実践しはじめた。有機農研の結成は、個々バラバラに存在していたこれらの消費者、生産者を結びつけ、相互の連帯を促した。
結成を呼びかけたのは、当時の協同組合経営研究所理事長一楽照雄であり、自然農法を実践する福岡正信や、食べものと健康との強いつながりを指摘した医師・梁瀬義亮、農薬禍を憂える農村医学の創始者若月俊一らに触発されたからである。結成集会には29名が参加し、初代代表幹事に塩見友之助 (元農林事務次官) 、常任幹事に一楽照雄ほか3名、そして土壌微生物の重要性を説く足立仁、横井利直、自然農法の指導者露木裕喜夫など11名を幹事に選出した。
会の名称に使われた「有機農業」という言葉は、後に一楽照雄が邦訳した『有機農法』(ロデイル著、原題 Pay Dirt ) にヒントを得たものだが、漢書にある「天地、機有り」からとったものだ。「機」とは、英語ではダイナミズム、自然の原理、天地の動きには法則があるという意味であり、農業というものは、自然の原理に順応してそれを助け合うものであることを表している。後にはさらに、特に生産者と消費者の間の「有機的な人間関係」を築くことが重要であるという意味あいも付与された。
現在の有機農研の会員は約 4,000名。生産者会員は20~25%で、消費者会員が多く、農学者、医学者、経済学者、協同組合関係者、農業ジャーナリストなども参加している。機関誌として『土と健康』を毎月発行し、また月例研究会、有機農業入門講座 (年間2回以上)、果樹研究会や土づくり研究会、総会(年間1回以上)を開催して会員の相互交流と有機農業運動の普及に努めている。有機農研の「結成趣意書」「規約」に示された趣旨に賛同する人は誰でも会員になることができる。
2. 背景・・工業化と農業近代化の進展
日本はほぼ温帯モンスーン地帯にあり、日照時間が長く、降雨量が多く (年間1200~3000ミリ) 、春夏秋冬の四季がはっきりとしている。国土の7割は森林であるが、多くの河川と肥沃な土に恵まれている。農家の耕地面積は狭く、現在でも1.5 ha以下が8割弱を占める。畑では年間2~3作の作物を輪作し、田は裏作に麦や野菜をつくり、多種多様な野菜や穀物、果物を作ってきた。米は主食とされてほぼ全国で作られており、水田による洪水調節、地下水涵養などの環境保全機能が改めて見直されている。
日本の農山村は、第二次世界大戦の敗戦(1945年) によって荒廃した。深刻な都市部の食糧難に対して、農民には食糧供出が強要されるとともに、農業には緊急増産の課題が課せられた。他方、占領政策の下で農地解放が行われ、長年農民を苦しめてきた地主-小作関係は解消した。農家の生産意欲は高まり、伝統的な農業技術に工夫・改良が加えられ、生産性が高まった。ほぼ60年代までは、周辺の河川・海、山林などの活用も含め、地域に根ざした自給を基礎とした有畜複合の農業と自給的な食生活が営まれてきた。
だが、1954年には軍事援助(MSA協定) にからんでアメリカの余剰小麦の受入れが決まり、その後の農産物輸入に道を開くことになった。1960年以降の高度経済成長期には、政府や財界主導の自然破壊・農村破壊を伴う工業化や開発が進み、農村から都市に労働力が流出した。1961年に制定された農業基本法の下では、生産性を第一にした農業が推進され、大規模・専作化、機械化、施設化、畜産と耕種部門の分離、農薬・化学肥料、石油エネルギーなどに過度に依存した近代農業が広く行われるようになった。
その結果、・兼業化のさらなる深化、・農業労働力の劣弱化と枯渇(老齢化・女性化・後継者不足・嫁不足)、・耕地利用率の低下(裏作など労働報酬の低い作目の生産放棄)、・有機質不足による地力の減耗(堆厩肥づくりの放棄)、・大規模・単作化に伴う連作障害の多発、・農業生態系の単相化による病害虫の多発、・農薬による人体・農畜産物・土壌・地下水・河川水・空気の汚染、・畜産公害の深化(量産家畜や家禽類の過密多頭羽飼育)、・耕地の人為潰廃の進行、・耕作放棄地の増加、そして・食糧自給率(特に粗粒穀物)の低下が続き、畜産用飼料の輸入増大が続くなかで、・一部農畜産物(米・牛乳・卵・柑橘類)の生産過剰など、日本農業は危機的状況になり、農村は疲弊し、農畜産物は農薬や動物医薬品(飼料添加物)で汚染された。この状況は、今も続いている。
1980年代に入ると、過度の工業製品の輸出による貿易収支の大幅な黒字の解消のために、農産物輸入が一層推進された。食糧自給率は、熱量でみると1991年には46%にまで落ち込み、飼料用も含めると数量で29%に低下した。1992年6月には、今後の中長期の「新しい食料・農業・農村政策の方向」(新政策)が策定されたが、国際競争力をつけるために一層の効率化を進める大規模化や、農業の経営主体の法人化が前面に出ている。環境保全型農業の推進も盛り込まれてはいるが、具体的な農薬削減計画などはなく、有機農業についても、中山間地域の振興策の一つとされるだけの消極的な位置づけしかされていない。
農村は、都市の膨張、ゴルフ場やリゾート地としての開発によってもむしばまれている。工業偏重の中で、農業、農村、農民が切り捨てられ、同時に伝統的な生活文化や、食料の自給・自立もないがしろにされている。農業の将来性に展望が持てず、後継者も少なく、新規就労者も年間約1800人という少なさである。だが、ごく少数ではあるが、都市でのサラリーマン生活をやめて有機農業に活路を見出そうとする若者も出てきている。
3. 有機農産物流通の現状
(1) 最初は「提携」から
有機農研に集う生産者と消費者は、1970年代から生産者と消費者の「提携」という方法で有機農業を進めてきた。「提携」は、既存の市場流通(卸売市場経由)に依存しない、自主的な「もう一つの流通」を創出することともいえる。形態はさまざまであるが、基本的には、図2に示したように、特定の生産者(生産者グループ含む)と特定の消費者(消費者グループ、生協など)が話し合いや交流によって相互理解を深め、双方が自ら労力や資金を出し合い、自主的で独自の配送によって継続的に農産物を取り交わす産直であり、生産者の拠点から消費者の拠点(配送ポスト、ステーションなどと呼ばれる)に3~10数世帯の会員が各自取りにいくという共同購入方式である。
日本の有機農産物の流通はこの「提携」によって始まった。次節で詳しくみるように、「提携」は、単に自主的な「もう一つの」流通方法をつくりだすことにとどまらず、そのような方法で農産物を取り交わす相互交流の中で、生産の場においても、消費の場でも、あるべき姿に向かう変革をうながすダイナミックなものである。
(2) 増える市場流通
1970年代後半になると、「提携」運動で取り交わされる安全な有機農産物に着目し、有機農産物を独自のルートで、専門に取り扱う業者や八百屋等が現れ、少し遅れて自然食品店、デパート、スーパー・マーケットでも取り扱うところが出てきた。
1980年代に入ると、特に1986年4月に起きたチェルノブイリ原発事故後の食品の安全性への関心の高まりから、消費者の有機農産物への需要が急増した。これに対応して、有機農産物を「儲け」の対象とみなし、既存の市場流通機構によって広域市場流通にのせ、差別化による高付加価値商品化をねらう「業者」の参入が活発化した。
そのことは同時に、まがい物の氾濫をもたらした。「有機栽培」「無農薬」「省 (低・減) 農薬」「自然農法」「微生物農法」などの有機類似の表示で、高めの価格で売る店がふえた。
(3) 表示規制の現状と問題点
農林水産省は、1992年10月1日、「有機農産物等に係る青果物等特別表示ガイドライン」を制定し、1993年4月1日から施行した。さらに、同年6月11日には従来は加工食品の規格とその表示を定めたJAS法 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律) を改正して、「特定JAS規格」 (作り方JAS:生産方法の基準) を新設した。これにより、今後、行政主導で有機農産物の基準を特定JAS規格として作り、行政主導により認証を行っていこうというものである。
しかし、有機農産物を「儲け」の対象とみなす業者の主張をいれて農林水産省が作った定義・基準は、節減農薬使用のものも含み、あいまいで問題が多い。「物質循環と生物循環を重視する健全な有機農業の発展」を阻害すると、主だった消費者団体も強く反対してきた。有機農研としても是認できるものではない。
このような日本の表示規制・基準づくりは、欧米のものとはかなり性格を異にする。欧米では、有機農業生産者団体が経験と実績に基づき、自主的な基準づくりを主導してきた。制度がつくられる過程において「民主的」な方法がとられていない日本の現状では、それが運用される場面においても「民主的」に行われるという保証はない。一方的な管理になり、健全な有機農業の発展を阻害するおそれがある。
4. 市場流通指向型の生産の問題点
さらに付け加えると、たとえ基準と認証制度の作られる過程および運用方法が「民主的」であっても、健全な有機農業の発展にとっては問題が多い。とりわけ、今日の日本の卸売市場制度にみられる中間業者を幾重にも通した市場流通は、生産者と消費者を分断し、相互に物事の本質を見えなくしている(図3参照)。そのため、有機農研に集う生産者と消費者は、「提携」という「信頼を土台にした相互扶助関係」を継続的に取り結ぶことで、産地開発や集荷・品揃えなどの市場機能を自前の方法を工夫して代替し、有機農産物を入手してきた。
なぜなら、安全性よりも見栄えや流通の効率を優先させる市場のしくみが、生産や消費をゆがめてきたからである。しかも、市場流通は、有機農業の「農法および経営の永続性」を保障しない。特に以下の2点が指摘できる。
1.市場は、高付加価値を保障しない
市場価格は、需給関係のバランスにより形成される。市場への新規参入者が増加し、生産量が増加するにつれて、価格は低下する。現状の高値は、慣行栽培農産物よりも有機農産物の供給が不足しているからにすぎない。
2.頼りにならない「消費者ニーズ」
食べ方のゆがみが作り方のゆがみをもたらすという自覚と反省のない「消費者のニーズ」は、「虫食い跡のない、粒そろいの、外観のよい、おいしい、安全な農産物。必要な時に必要な量を、いつでも、安価に・・・・」と、続く。それは、際限のない商品差別化競争と価格競争をもたらし、生産者にも競争を強いる。しかも、高値の有機農産物の需要は、不況が長引いたりすれば落ち込む、不安定なものである。
生産者と消費者が互いに「顔も暮らしもみえない」市場においては、有機農業の永続性はこころもとない。「提携」は、これに代わる「もう一つの途」である。
5. 生産者と消費者の「提携」を軸にした有機農業運動
(1) 「提携」の基本理念
「農薬や化学肥料を使わない農業、それが有機農業であるというだけの単純な解釈にとどまっていると、今日の社会のいろいろな矛盾を看過することになる。」( 一楽照雄)
日本の有機農業運動は、現代の農業技術体系や経営形態、農業労働観、流通システム、農産物の消費構造、および農業政策などの持つゆがみをそれぞれ問い直し、農業を本来の「あるべき姿の農業」に取り戻し、同時に流通のあり方や食生活を改善し、生活の変革を実践する等身大の草の根運動である(図1参照)。
つまり
・農薬問題は、単に農法だけの問題ではなく、流通・消費・農政などの総合的な矛盾の象徴であり、「構造悪」として現出しており、・肥大した市場流通や食品産業などが、生産者と消費者を分断し、生産のあり方をゆがめ、また消費(食べ方)をゆがめている。・したがって、消費者も、このような悪循環を形成している「無意識の加担者」であり、・これらを是正するには、生産者と消費者が直接、有機的な人間関係を築き、「生産者と消費者の顔と暮らしの見える」関係のなかで、協力しあいながら運動を進めていくことが大切である、と考えてきた。
そのなかで獲得されてきた特徴的な方法が、生産者と消費者の「提携」/「産消提携」である。これは、単に流通方法だけでなく、農産物を取り交わすことを通した相互作用のなかで、生産の場においても、消費の場においても、それぞれダイナミックな変革をうながしていく。
(2) 「提携」の方法
・ 自給を基礎にした循環的な農業
食べ物は、いのちを育むものであり、農耕の基礎はまず家族のための自給にある。自給を基礎に据えた農業は、多種多様な品目を少量ずつ作り、畜産を組み合わせた有畜複合小農経営となり、堆厩肥・飼料・種子なども自給する循環的な農業である。「提携」は、このような自給を基礎とした農家の食べ物を都市消費者が「分けてもらう」ことが基本であり、「農家の食卓の延長線上に、消費者の食卓がある」。
ここでは食べ物は、売って儲けるためのものではない。したがって、工業製品のような効率を求めず、大量生産のために危険な農薬・化学肥料などは使わない。自然のもつ本来の生産力を引き出すために、できるだけ自地や地域の有機物肥料を循環的に使う、自然と共にある生命に満ちた農業をめざす。
・ 消費者が農作業を手伝ったり、体験する。
効率を求めず、農薬・化学肥料を使わない農法は、手間がかかる。「提携」では、この農法転換の労力を軽減させるために、消費者が農作業を手伝いにいく(縁農)。手伝いの度合いはグループによって異なるが、消費者が農作業を体験したり、畑をみることを通して、農家や農業を理解する一助にもなる。
・ 選別・包装の簡略化
既存の卸売市場では、見栄え、大小・粒揃いなどの規格、一定以上の数量や品揃えが要求されることも、慣行農法で農薬・化学肥料の使用が不可欠である理由である。「提携」では、泥つきのものでも、また大小が混在するものでも無選別で消費者に届ける。包装も簡略化し、手間を省いている。
・ 自主配送
農産物は、生産者または消費者がみずから配送する。生産者にとっては「誰が食べるのか」がわかり、また、消費者にとっては「誰が作っているのか」、お互いの「顔」がみえる。話し合いや農作業の手伝いなどを通して、お互いの暮らしもみえてくる。「提携」は、生産者と消費者が人と人との友好関係を築くことを基礎にしている。
・ 食べ方の変革
「提携」では、消費者もまた、食べ方や買い方を変革している。つまり、消費段階では;
・畑でとれたものは、多寡・形状の如何を問わず、消費者が全量引き取る。
・すべてを消費するよう、「間引き菜からとうが立つまで」「葉っぱから根っこまで」食べ方を工夫する。
・畑でとれたものは、多寡・形状の如何を問わず、消費者が全量引き取る。
・畑に合わせて食べる・・献立に合わせた食材の選択ではなく、四季折々の自然の恵みに合わせた献立を工夫する( 季節のものを食べ、旬以外のものは欲しがらない)。
・ 価格の決め方
「生産者は消費者の生命に責任を持ち、消費者は生産者の生活に責任をもつ。」
価格については、生産者と消費者が直接話し合って、相互に納得できる価格( 提携価格) を設定する。これは、生産者からみれば慣行栽培農産物の市場出荷価格(生産者手取り価格)よりも高く、消費者からみれば慣行栽培農産物の市場価格程度に抑えられている場合が多い。「提携価格」は、生産者の生活費や生産費の保障を内容としており、単なる需給バランスの上に成立する「市場価格」とは明らかにその含意が異なる。
さらに、力量に応じて、農法転換後の減収補償、農業基金( 無利子融資) 、災害見舞い金などの仕組みをつくっている消費者グループもある。
以上のような「産消共生システム」の構築によって、消費者も生産に伴うリスクを分担し、生産者は農産物の豊凶や市場の価格動向に左右されずに、比較的安定した農業所得を得て、「経営として」の永続性を獲得している。それは同時に「農法として」の有機農業を永続的にし、その結果として消費者グループは「食べ物として」、安全な有機農産物を安定的に入手することが実現されている。
このような運動の経験は、1978年11月、「生産者と消費者の提携の方法についての10原則」として集約された。その後は意識的にこうした「提携」運動を軸にした有機農業運動が展開されてきた(提携の10カ条参照)。
6. 地域自給と自立をうながす有機農業運動
以上みてきたように、「提携」運動では、農家の自給を基礎にした「顔と暮らしのみえる関係」の中で、農家の食卓がそのまま都市消費者の食卓につながっている。豊かな農業は、豊かな食卓を生み出す。その多くは、有畜複合経営、多品目少量生産の経営であり、それは、地域の自然の多様性を活かし、環境にきめこまかに調和した農法でもある。「提携」では、農家の自給に加え、その地域の中での山林や河川、地域内の小規模の食品加工業者や消費者との有機的な関係の中での「地域自給」という考えも獲得されてきた。このような有機農業は、地域という広がりをもちながら、地域の自立をうながしている。
有機農研では、会合などの機会あるごとに、生産者が自ら採取した良い品種の種を交換する種苗交換会を開催している。種子についても農家の自立を図り、有機農業にふさわしい品種を自分たちで作り、広めていくためである。また、海外との交流にも努め、フィリピン・ネグロス島での自給的な農業の指導を行ったり、国内農家・農場が外国からの研修生も受け入れ、技術の交流に努めている。
今日、有機農業生産者と直接提携する消費者グループは、全国でおよそ 800~1000グループあると推定されている。その規模は、10世帯未満から5000世帯以上まで、多様である。近くの生産者との地域内提携を中心に、数戸から数十戸の農家と提携している。ほかに、生協 (全国に約 650の地域生協、組合員数約1600万人) も提携・産直を行うところがふえている。
しかし、会の結成から22年を経た現在、産消提携運動はいくつかの課題に直面していることも現実である。消費者グループに関しては、リーダーの高齢化と運営委員の固定化、女性の就業・社会参加の増加に伴う会活動の担い手不足、宅配や店頭販売など有機農産物の入手機会の多様化にともなう消費者の共同購入離れなど、また生産者・生産者グループに関しては、慣行栽培農家ほど顕著ではないが、やはり生産者の高齢化と後継者不足の問題があり、提携消費者グループの会員数の伸び悩みから派生する消費量の減退の問題もある。
だが、今日、「提携」の意義は、かえって重要性を増している。;
・輸入農産物の増大や企業の進出の中で、自給に基礎をおいた自立的な農業が重要であること、
・環境問題、食品の安全性問題から、ますます有機農業が重要になってきていること、
・有機農業運動に生産者だけでなく、消費者が参加して自立的な食料供給システムをつくることがますます重要になってきていること、
・提携」を通して、生活と社会の基礎に農業を据えることを広げていくことが、持続可能な社会につながること。
このような意義を踏まえ、来るべき21世紀を見通して新しい時代にふさわしい「提携」をいかにして広範につくり出していくかが課題であろう。
7. 今後の方向
そのためには、まず、過去20余年間に蓄積した経験と知識を整理してさらに深めていくことが大切である。特に、欧米型の技術ではなく、雨の多いアジアの自然に根ざした農法をさらに研究し実践していくことが求められる。そして、「提携」の方法や食べ方などの各人・各グループの個別の経験知を広く会員やこれから提携運動に取り組もうとする人びとに共有されるよう、工夫していくことも必要であろう。
また提携グループ間の交流や連携を強化し、あるいは市民・環境・消費者運動団体など他団体とも積極的に交流していくこと、生協や農協との経験の交換や、行政 (国や自治体) に対して産消提携運動の意義を積極的にアピールすることも必要であろう。
そして、有機農業を日本の農政の根幹に位置づけさせ、有機農業の健全な発展に資する政策提言を行うことなど、あらゆる機会をとらえて経験や知識を交換し、農法においても経営においても永続性のある有機農業を積極的に進めていきたい。
IFOAMにおいても、従来の基準認証を中心とする市場指向の運動だけではなく、それと同時に、このような「地域自給」を基礎にした「提携」運動を根幹に据えるべき時期にきている。
日本有機農業研究会
〒162-0812
東京都新宿区西五軒町 4-10 植木ビル 502号室
TEL : 03-6265-0148
FAX : 03-6265-0149
E-mail : info@1971joaa.org
URL : https://www.1971joaa.org
COPYRIGHT © 2009 JAPAN ORGANIC AGRICULTURE ASSOCIATION, ALL RIGHTS RESERVED.
